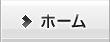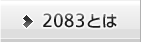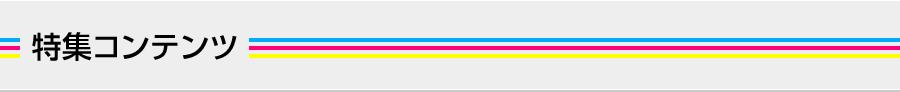取材・文:hide / 永芳 英敬 撮影:中村ユタカ
『クロノ・トリガー』『ゼノギアス』などのゲーム作品のみならず、近年ではアニメ、ドラマの音楽など、多彩な活動を展開する作曲家・光田康典氏。作家20周年の節目を迎えた光田氏に、これまでの音楽活動におけるこだわりの数々や、若い頃の経験談、そして今後の活動における展望をお聞きしました。
光田 康典 プロフィール
Yasunori Mitsuda Profile
■ミュージシャンの皆さんと共に作った「時の傷痕」
―― 光田さん、作曲家活動20周年おめでとうございます!
光田 ありがとうございます!
―― 今回は、光田さんのこれまでの活動を振り返りつつ、今後の活動の展望についてお聞きしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。
光田 こちらこそ、よろしくお願いします。
―― これまで光田さんは、本当に多くの作品の音楽を担当されてきましたが、今までに作曲された楽曲の中で、特に思い入れの深いものはありますか?
光田 本当にたくさん作ってきましたね。先日、僕が今までに作った楽曲を全部リスト化して数えてみたんですけど、CD化されていない楽曲も含めると、だいたい1,400曲くらいあったんですよ。
―― 1,400曲ですか!
光田 ええ。もうあんまり覚えていない作品もありましたけど(笑)、どの楽曲もそれぞれ思い出がありますね。その中から1曲挙げるとするなら、やっぱり『クロノ・クロス』の「CHRONO CROSS 〜時の傷痕〜」(以下「時の傷痕」)です。僕の場合は、コンピュータに楽曲を打ち込んでシミュレーションした後レコーディングすることが多いんですけど、「時の傷痕」は、レコーディングで劇的に素晴らしくなったんですよ。僕が打ち込みで作った原曲よりも、もう何倍も良くなったんですね。だからあの曲は、僕ひとりの力で作ったものではなくて、ミュージシャンの皆さんと一緒に、みんながひとつの想いで作ったから、世界に通用するような楽曲に仕上がったと思うんです。そういうことって、なかなか珍しいですね。
僕って、常に新しい人と何かをやりたいという思いがあるんです。でも、新しいことにチャレンジするということは、以前使った技みたいなものが使えないこともあるわけですよ。そうなると失敗しちゃうことも多々あるんですけど、「時の傷痕」のように、いろんな人の相乗効果で、自分が想像していた以上のものが出来あがったというのは本当に稀なケースなんです。最初、打ち込みで原曲を作った時は、「こんな曲で、大丈夫かな?」と思っていたんですけど、ミュージシャンの皆さんのおかげで素晴らしい楽曲になりました。
■前に突き進んでいくキッドに共感
―― 光田さんは、物語や、その中に登場するキャラクターに合わせて音楽を作るということが多かったと思うんです。光田さんの中で、特に思い入れの深いキャラクターはいらっしゃいますか?
光田 キャラクターですか。僕の中ではやっぱり、『クロノ・クロス』のキッドが非常に印象に残っていますね。
―― どのような点が印象的でしたか?
光田 彼女の生い立ちや設定に、共感できる部分がたくさんあったんですよ。僕も『クロノ・クロス』の制作当時はまだ20代だったんですけど、ひとつのものにがむしゃらに向かっていく感じがとても好きで。すごく共感できました。
―― なるほど……キッドといえば、やはり「星を盗んだ少女」という楽曲が印象深いです。キッドのテーマともいえる楽曲ですけど、光田さんの中でもやはり思い入れが深いのでしょうか?
光田 そうですね。あの楽曲って、最初はスーパーファミコンのサテラビューで配信された『ラジカル・ドリーマーズ -盗めない宝石-』というアドベンチャーゲームのために書いたんですけど、その当時からキッドという少女がすごく印象的だったんですよね。色々なものを背負っているけれど、前向きに、怒りをパワーにして前に突き進んでいくというキッドの姿勢にすごく心を打たれましたね。僕自身もそうありたいなという想いもあって、キッドはとても好きなキャラクターなんです。
■探し当てるように作った「SMALL TWO OF PIECES」
―― これまでに作られた楽曲の中で、いちばん苦しかった、難産だったものはありますか?
光田 『ゼノギアス』エンディングテーマの、「SMALL TWO OF PIECES 〜軋んだ破片〜」ですね。あれは本当に難産でした。僕が会社で曲を作っていた時も、「これでいいのか? これでいけるのか? どうなんだ?」みたいにずっと模索しつづけて。家に帰ってもひたすらコンピュータに向かって作ったり、何度もファイルをごみ箱に捨てたりの繰り返しでした。ひどいときは、ゴミ箱に捨てて小一時間ほど考えたあと、ごみ箱からまたファイルを戻して……というようなことをやっていたんです。
―― 相当、悩まれたんですね。
光田 はい。当時はオートバックアップも無かったので、捨てたらもう、それで終わりなんですよ。何度もごみ箱を空にするところまでやろうとしていたんですけど、でもなんとなく、原石というか、光るものがあると感じて……ちょっと気になっていたんですよ。「もうちょっと何とかすれば、いい曲になるんじゃないか」という感じだったんです。
―― 探し当てるような感じだったのでしょうか。
光田 探し当てる……。そうですね。本当に、作曲って作業はそういう感じです。パーッと作って、はい、できました!というものじゃなくて、僕の場合は「このコードで本当に正解なのか?」「このメロディで本当にいいのか?」っていうのを、何度も何度も聴きながら、繰り返し練っていくんですよね。だから時間はかかりますけど、やっぱり僕は皆さんの印象に残る楽曲を作りたいと思っていますからね。あれは本当に難産でした。でも、ジョアンヌ・ホッグの歌が曲に入った瞬間に、本当に救われた気持ちになりましたよ。「これ、捨てなくてよかったなぁ」って。報われました。……もし、あれを捨てていたらどんな曲になっていたんでしょうね(笑)。それはちょっと聴いてみたいかな。
■“テーマ”を決めてつくる
―― 光田さんはこれまで多数の作品を手がけられてきましたが、ご自身が作曲家として最も成長できたと感じる作品はありますか?
光田 僕が今までに手掛けた作品すべてですね。何かの作品を作るたびに勉強になります。僕の音楽の作り方としては、作品ごとに“テーマ”を決めてやるんですよ、常に。
―― “テーマ”ですか。
光田 ええ。何か自分の苦手なこと……たとえば、オーケストレーションが苦手だったらそれを克服しようとか。何かの楽器が不得意なら、その楽器をとことん研究してやってみようとか。そういうことですね。
僕、『クロノ・クロス』の頃はギターが苦手だったんですよ。サウンドとしては好きなんだけど、演奏するとなると、どんなふうに弦を押さえたらいいか分からない(笑)。なので、その頃からギターを買って勉強して。『クロノ・クロス』はギターサウンドで行こう、というテーマがありました。
『クロノ・トリガー』はいろんな時代に行くので、いかに楽曲のモチーフを組み合わせて印象的なゲームにしていくか、ということがテーマでしたし。『ゼノギアス』は、生録音の音楽や、歌ものを入れるというテーマでした。それぞれの作品にテーマを設けて作ってきましたね。
―― 『ゼノサーガ エピソードI』では、オーケストラでの音楽を作られていましたね。
光田 そうですね。初めてオーケストレーションをしました。それまでにも勉強はしていたんですけど、やっぱり書物で勉強しているだけのものと、本物のオーケストラで実際に演奏してもらうのとでは、大きな差があるんですよね。音楽理論的に説明されていることでも、その通りにやっても意外に綺麗に鳴らなかったりするんです。それは何故かと言うと、ミュージシャンの気持ちもあるし、技量もあるし。スタジオの状態やエンジニアの技量など、本当にいろんな要素があるんです。
そして、理論というのは「大体うまくいくであろう」ということが本になっているわけですから、それをその通りにやったからって、必ずしもうまくいくわけではないんですよ。やっぱり色々と四苦八苦して、オーケストラと共に、自分の納得がいくサウンドを作り上げていくわけです。とにかく経験あるのみなんですよね。何度も失敗しては自分の理想に近づいていくわけです。間違いなく『ゼノサーガ エピソードI』の時よりも、今のほうがオーケストレーションの技量は上達していると実感しています。作品ごとに学ぶことは多いですよ。そういった意味では、やはりテーマを設けて作っていくのは、僕にとってすごく重要なことですね。
―― 作品ごとに新しいことに挑戦して、勉強して、よりよいものを作るということですね。
光田 はい、勉強して。……まあ、大変ですけどね(笑)。
―― 光田さんはいい音を録るためなら、自腹で費用を出してでもレコーディングを続行することがあるとお聞きしたのですが。
光田 そうですね。やっぱり自分が胸を張って、「この作品はお気に入りなんです」って言える状態にしないと。多少お金がかかっても、もう1回レコーディングしていい音が録れるんだったら、やればいい話じゃないですか。それを、数万円とか数十万円をケチって作品の質が下がるのは、ユーザーの皆さんに対しても失礼ですからね。ユーザーの皆さんは、お金を出して作品を買ってくれるわけですし、やっぱり、それ相応の作品を提示するというのがクリエイターの義務だと思います。僕自身が胸を張って出せるような作品を、これからも常に作っていきたいですね。
■『シャドウハーツ』の弘田佳孝氏と共作して気づいたこと
―― この20年の中で、転機になった作品はありますか?
光田 転機になったのは、『ゼノサーガ エピソードI』を終えた時ですね。あの作品の音楽を作り終えた時、僕の中で完全にからっぽになっちゃったんですよ。今思えば、特に完璧ではなかったのにも関わらず、自分はやり尽くしたような気になっちゃって……。もうロンドンフィルでレコーディングしたし、もうやること無くなっちゃったなって、勝手に思っちゃったんですよね、その時。
で、当時はずっと曲が書けないまま、『シャドウハーツ』という作品を担当することになって。この作品では、弘田佳孝君という作曲家と一緒に音楽を作ったんです。彼は現在、EARTHBOUND PAPAS(植松伸夫氏がリーダーを務めるバンド)のベースをやってますね。じつは彼と僕は、音楽学校が同じで、同級生だったんですよ。
―― そうだったんですか。
光田 ええ。スクウェアで効果音の制作者が必要になった時に、彼を招集して効果音を作ってもらうことになって、そこからゲーム音楽の世界に入ってきたんですけど。彼はもともとすごいロックとか、そっちの方向の人間なんですよ。で、彼と一緒に『シャドウハーツ』の音楽を作ることになったんですけど、僕は当時完全に抜けがら状態になっていたので、正直に言って、あんまり気が進まなかったんですよね。でも、一緒にやって気づいたことがあるんです。彼の音楽スタイルって、非常にアバンギャルドで発想が大胆なんですよ。音の鳴りが良いとか悪いとかじゃなくて、“今、この音が欲しいんだ!”みたいな、そういうパワーをすごく感じて。「そうだな……音楽って、そもそも綺麗に作ろうとかじゃなくて、自分が欲しい音を鳴らせばいいんだ」ということに気づかされたんです。
―― 弘田さんと共作することで、そう感じられたのですね。
光田 そうですね。音を置くのが怖い時期でもありましたので、彼とやることによってもっと自由に音楽を作ればいいんだ、と気づきました。自分がずっと悩んでいたことが、少し緩和された感じでしたね。
―― ある意味、吹っ切れたような。
光田 うん、吹っ切れた部分はありますね。結果的に『シャドウハーツ』の音楽は、僕の中でも非常に特殊なサウンドになったと思うんですよね。なので、あれは僕のひとつの転機になりましたね。『ゼノサーガ エピソードI』から『シャドウハーツ』の間は、僕の中ではすごく葛藤があったんですけど、非常に重要な時期だったと思います。
■演劇から学んだこと
―― では次に、だいぶ昔のことになるのですが、光田さんの若いころのお話をお聞きしていきたいと思います。光田さんは学生時代に演劇の音効さん(音響効果)をされていたそうですね。
光田 はい、やっていました。
―― その時のご経験で糧になったことはありますか?
光田 当時、とある劇団の専属音効をしていまして、完全に任されていました。まあ、しがない小さな劇団だったので、ノーギャラでやるようなレベルですけどね。お客さんも本当にまばらで50人入ればいいほう、みたいな劇団だったんですけど。選曲から音の当て方まで、全部好きなようにやっていいよっていうことで、僕が知っている曲を当てたり、足りない曲は自分で書いたりして音楽を流していたんですよ。
その経験から勉強になったのは、「セリフと音楽の関係」ですね。間があって、ここのタイミングで音楽が流れ始めるとか。静寂の中の一拍、みたいな。ああいう本当にちょっとした間で、人間の感情って大きく左右されるんだな、ということをその演劇で学ばせてもらいましたね。それがたぶん『クロノ・トリガー』にも息づいていると思いますし。音楽と映像、音楽と俳優の演技、音楽とセリフ……そういったことを考えて、ベストなタイミングにベストな音楽を鳴らす、という。そういうことを学ばせていただいた場所でしたね。
■桜庭統さんのアシスタント時代のお話
―― 光田さんは、桜庭統さんのアシスタントをされていたことがあるとお聞きしまして。
光田 はい。
―― 桜庭さんがウルフチーム(※)に在籍されていた頃ですよね。
※かつて存在したゲーム制作会社。日本テレネット内の開発チーム「ウルフチーム」が独立し、1987年に設立された。
光田 そうです。僕がまだ18歳の頃ですね。当時僕は東京に来てアルバイトを探していたんですけど、どうせアルバイトをするなら何か音楽関係の仕事をやりたいなと。やっぱり音楽漬けになりたいという思いがあって、色々探してたんですよ、フロムエーとかで(笑)。そしたらゲーム開発で、シンセサイザーマニピュレーターの募集があって。そこがウルフチームだったんです。会社の場所も、当時僕が通っていた学校から近くていいなと思って応募したら、受かっちゃったんです。
で、いざ中に入ってみたら、僕の隣の席で、桜庭さんがキーボードでガンガン曲を書いてるんですよ。僕はFM音源で楽器の音色を作るんですけど、もう、桜庭さんからどんどんどんどん曲があがってくるんですよ。本当に1時間に1曲くらいのペースで作ってて。
―― 桜庭さん、当時から作曲速度が早かったんですね(笑)。
光田 うん、メッチャ早いんですよ。桜庭さんが「これ、できたから音色よろしく」って曲を渡してくるんですけど、もう僕が音色を作るほうが間に合わないんですよ(笑)。早すぎるでしょ!って。
―― (笑)。すごいですね…!
光田 すごかったです、本当に。もう、弾いたらOKみたいな感じですよ。キーボードを弾いて、どんどんベースやドラム入れて、はい、終わりみたいな。それでクオリティが低いかっていうと、全然そんなことはなくて、ちゃんとした音楽になってるんですよね。桜庭さんの手クセは入ってるんですけど、クオリティ的には、当時のゲームの音楽としては非常に高かったんです。
そうやって桜庭さんから曲をもらって、僕は「じゃあ、このサウンドならこういう音がいいですよね」とか言いながら、FM音源で音色を作っていました。当時はパソコンゲームですから、PC-98とかPC-88の時代ですね。
―― FM音源が主流の頃ですね。
光田 そうですね。それにプラスして、PCM音源もちょっと入っていたぐらいだと思うんですけど。そのマニピュレーターをやっていました。
―― 光田さんが、桜庭さんから学んだことはありましたか。
光田 それが、あまりお話する機会がなかったんですよ。桜庭さんはずっと無口で、ひたすら曲を書く方でしたから。で、定時になったら「おつかれ」と言って帰っていって。あと、僕の作った音色に対しても、「この音色はイヤだ」とか、そういうことは一切言わなかったんですよ。
―― リテイクは少なかったのでしょうか?
光田 リテイクは、ほんとに数回だけでしたね。「ちょっとベースの音が柔らかいね」とか。「わかりました」って直したりしてね。
―― では、お話しされるのも本当にそういう時だけだったんですね。
光田 うん、そのくらいしかしゃべらなかったんですよ。でも、当時のことを桜庭さんは今も覚えてくれていて、お会いすると「いやー、あの光田君がねぇ」と言ってくれます。まあ僕は、1年ぐらいでウルフチームを辞めちゃったんですけどね。当時は機材の進化が目まぐるしかったんですよ。FM音源もあれば、加算式シンセだとか、アナログシンセ、サンプラーも色々ありましたし。あとPCM音源もどんどん進化していきましたから、その中でずっとFM音源で音色を作る意味合いを見い出せなくなっちゃった部分があって。
でも、曲を書かせてもらいたいと思ったことはないんですよ、当時は。ウルフチームで働いていたのは、音色作りとか、ゲームってどんな風に作られているんだろう?というのを学びたかったからなんです。とっても勉強になりましたね。
そういえば、当時スゴかったですよ、ウルフチームって。今では当たり前ですけど、カードをピッてやると、ドアがヒューッと開いて。「おーすげぇー、SFだーここ!」みたいな(笑)。「なんだここ! 『2001年宇宙の旅』にやってきたのか!(笑)」みたいな未来感に圧倒されましたね。すごくいい思い出です。
■効果音制作の醍醐味
―― 光田さんは『クロノ・トリガー』で作曲を担当される前に、効果音を担当されていましたよね。
光田 はい。いわゆるマニピュレーターもそうですね。
―― 光田さんが効果音を担当された作品は、『ファイナルファンタジーV』、『聖剣伝説2』、『ロマンシング サ・ガ2』などですよね。音楽を作るのとは、また違う面白さがありましたか?
光田 そうですね、非常に楽しくやらせてもらいました。『聖剣伝説2』はほとんど、ほぼ80%くらいは僕の作った音で出来ています。
―― 『聖剣伝説2』はクオリティの高い音楽でしたけど、効果音が鳴ると、その音で音楽が部分的に消えてしまうこともありましたよね。そのあたりの工夫は何かされていましたか?
光田 スーパーファミコンって、8トラックしかなかったんですよね。1トラック1音しか鳴らせないんですよ。菊田さん(『聖剣伝説2』の作曲家・菊田裕樹氏)が書いた曲はパーカッションが多かったので、多少は助かったんですけどね。まあたぶん、それは効果音で音楽が消されるだろうから、パーカッションを多めに入れよう、という風に菊田さんが考慮してくれたんだと思うんですけど。
で、効果音も、当時は2トラックを使って、ちょっとしたノイズ音でも、音をずらしてワイド感を出したり、モジュレーションを上手く使ったりとか、色々な技があったんですよね。でも当時2トラックで1つの効果音、たとえば「ザッ」という剣で斬る音を、2回連続で「ザザッ」というふうに鳴らしてしまうと、もうそれで4トラック使っちゃうことになるんですよ。そうすると残り4トラックしか無いから、ほとんど音楽が削られてよく分からない状態になってしまうんです。
だから、1音でちゃんと剣の音が成り立つようにしようと思いました。例えば、剣や足音のように頻繁に鳴る効果音ですよね。そういうものは1音で効果音を作っていました。大事なシーンは、すごくゴージャスに効果音を作ったりもしましたけどね。例えば『FFV』の飛竜の鳴き声とか。あれは非常に面白かったです。
―― 飛竜の鳴き声は光田さんが作られたんですね。
光田 はい、僕が作りました。
―― たしか、シルドラの鳴き声も光田さんが作られたんですよね?
光田 シルドラもそうです。動物の鳴き声系は全部僕ですね。
―― 当時『FFV』をプレイしていて、飛竜の鳴き声はとても印象的でしたよ。シルドラが渦に飲みこまれていってしまうシーンとか、すごく悲しげな声で。
光田 もう悲鳴みたいな感じですもんね。ぜんぜん実際の悲鳴には遠く及ばないんですけど。あと『ロマサガ2』も、ほとんど僕が効果音を作りましたね。ピコーンっていう音とか。
―― 電球の音ですね(笑)。
光田 はい。技をひらめいた時の電球の音ですね。イトケンさん(伊藤賢治氏)に、ラジオかなんかに一緒に出演しているときに「これもう1回作ってよ!」って言われたことがあるんですけど、「いや、今さら作れないでしょ!」って(笑)。
■SFC版『半熟英雄』の裏話
光田 あとは、スーパーファミコン版の『半熟英雄』で、すぎやまこういち先生が作曲した音楽のサウンドデザイン(ゲーム音源の制作)も担当させていただきました。
―― 『半熟英雄』も担当されていたのですか。
光田 はい、『半熟英雄』の音色を作らせてもらいました。すぎやま先生からスクウェアに、FAXで手書きの譜面が送られてくるんですよ。当時はまだ譜面なんです。MIDIデータの交換という概念があまり無い頃だったので、譜面がパーッとFAXで送られてきて。
その譜面をもとに僕がMIDIで打ち込んでいって、すぎやま先生のご自宅にお伺いして「こんな感じでどうでしょう?」とお聴かせしてチェックしていただいて。けっこう細かくアドバイスしていただきました。「マリンバがちょっと柔らかすぎる」とか、「エレピとフルートはこのバランスで」みたいな。あと、アーティキュレーション(※)のことをすごく言われました。「アタック(※)の位置はいいんだけど、リリース(※)が悪いね」とか。
※アーティキュレーション…… ある音から次の音へ、どのように移ってゆくかを表す音楽用語。音をなるべくつなげて演奏する「レガート」、音を短く切って演奏する「スタッカート」などがある。
※アタック…… 音の出だしのこと。
※リリース…… 音の鳴り終わりのこと。
―― すぎやま先生のアドバイスをもとに、MIDIデータを修正したわけですね。
光田 ええ。でも、FAXで譜面が送られてくると、譜面が潰れていて見えないことがあるんですよ。どっちとも取れる、みたいな。こっちでも間違いじゃないんだけど、こっちでも間違いじゃないとか。
そういう音を、「たぶん、これはこっちだろうな」って作って持って行くと、「光田くん、音間違えてるよ」って言われて(笑)。「だって譜面が見づらいんですもん!」とか心の中で思ってました(笑)。
―― (笑)。FAXですもんね。
光田 そうなんですよ。そんなやりとりがありました。でもすぎやま先生、とてもパワフルな方でしたね。その当時でもかなりのお歳だったと思うんですけど、バリバリに作曲されていましたよ。
■加藤正人氏と大ゲンカ!
―― 光田さんは若い頃かなり熱い方だったそうですが、光田さんご自身が昔を振り返って、「自分は熱かったなぁ」と感じる思い出はありますか?
光田 『クロノ・トリガー』を作っていた当時、加藤さん(加藤正人氏。『ゼノギアス』、『クロノ・クロス』など多数の作品で演出やシナリオを担当)のシナリオをプリントアウトして自分のブースで読んでいたんですよ。「曲をここに入れよう」とか考えながら。
そうしたら、どうしてもつじつまが合わない、「なんでこの設定なんだろう?」と思うことがあって。加藤さんのブースに乗り込んで、「これどういう設定してんの?こんなの全然ダメじゃん!」って話をしたんです。それですごい言い争いになったんです、加藤さんと。「これはこうで、こうだよ!」とか。挙げ句の果てに、「もうやってらんない!」って叫んで、紙っぺらを加藤さんに投げつけて、自分のブースに帰っていった覚えがあります。
―― えええ……!
光田 まわりの制作メンバーのみんなは、びっくりして一斉に立ちあがってましたよ(笑)。「光田と加藤がすっげえ大ケンカしてる……」って唖然としちゃって。そんなことがありました。加藤さんはその出来事を全然覚えてないんですけど、僕はすごく覚えてます。その設定に対してすっごく激怒した覚えがあります。若かったですね(笑)。今は絶対そんなことはないですけど。
―― 光田さんは、なぜそんなに怒ったのでしょうか?
光田 あれはね、サラの立ち位置でケンカになったんですよね。なんか最初、とんでもない設定だったんですよ、それが気に入らないって言って。
―― けっこう突拍子もない設定だったのですか?
光田 そうなんですよ。まったく意味がわからなくて。それでケンカした覚えがあります。加藤さんはたぶん「そんなことあったっけ?」って言うでしょうけど(笑)。
■若い人は、熱く突き進んでほしい
―― 光田さんは色々なご経験をされてきたと思うのですが、若い世代の方にアドバイスするとしたら何かありますか。
光田 アドバイスですか……まあ、僕は若い頃は熱かったので、今の若い人も、熱い感じなのがいいんじゃないですかね。何事も熱く(笑)。
―― 若いパワーで。
光田 そうそう。若い時しかできないことってたくさんあるじゃないですか。だから僕、若い人がなりふり構わず「これはどうなんだ!」みたいなことを言うのがすごく好きなんですよね。「これをやりたいんだ、なんでやらせてくれないの!」とか、そういう熱い人をみると、こっちも、「じゃあ、それをやってみれば」ってなりますし。特に、外国の人なんかどんどん自分をアピールして来るじゃないですか。「これをやりたいんだ!」とかね。そういう熱い気持ちを持ってる人って気持がいいですよね。結局それって、すごく自分に自信をもっていて、その事にたいして好きじゃないと出来ないと思うんですよ。
―― そうですよね。
光田 その物事に対してすごく熱くなれる、「誰よりも自分は熱くなれる」っていう、そういう想いが無いとなかなか良いものも出来ないですしね。逆に言えば、そういう気持ちが無いんだったら、物作りは辞めたほうがいいでしょうね。熱い気持ちをもって突き進めば、必ず成功すると思っています。
たぶん、誰しも自分がなりたいものや、やりたいことなどは実現すると思うんですよ。でも結局、その途中で熱が冷めちゃったり、現実に戻っちゃったりして諦めてしまうんですよね。もちろん、経済的な問題もあるだろうし、気持ち的な問題もあるだろうし、対人関係という問題もあるでしょう。でもそこを差し置いても、自分が何をしたいのか、何を表現したいのかということが、ぶれずに突き進める熱い人は、成功すると思いますし、たくさんライバルがいる中でも生き残っていけるんじゃないかなと思います。
■「遥かなる時の彼方へ」に込められた想い
―― 次は『クロノ・トリガー』に関するお話をお聞きしていければと思います。エンディングテーマ「遥かなる時の彼方へ」は、『クロノ・トリガー』のゲーム制作前に作られた、とある人のために書いた楽曲だとお聞きしました。どのような想いが込められている楽曲なのか、お聞かせいただければと思います。
光田 そうですね……実は、僕が高校生くらいの時には、すでにあの曲を作っていたんです。僕が高校2年生くらいの時だったかな。カモンミュージックというシーケンサーをバイトして買って、自分で色々と曲を好きに作っていたんですよ。
その当時に、大の親友が亡くなってしまって、その人のために書いた曲だったんですね。あの曲は本当に、思い入れがあるというか、別格です。何かのテーマがあって、ゲームに宛てた曲ではないので。ちょっとニュアンスが違うんですよね。
―― その曲を、なぜ『クロノ・トリガー』で使用することになったのでしょうか?
光田 『クロノ・トリガー』のエンディングと、なんかリンクしちゃったんですよね、僕の中で。別れは切ないけどちょっと前向きな、そういうイメージが。まあ、本当は使わないようにしようと思ったんですけど、『クロノ・トリガー』の最後のお話を読んでいた時に、なんとなくずっと気になってて。自分の経験とゲームの話と音楽がリンクしちゃって。
―― やっぱり使おう、と思われたわけですか。
光田 なんとなくですね。これはやっぱり使うべきだろうなと。あと、「遥かなる時の彼方へ」には、最後に『クロノ・トリガー』のテーマが入っていたりとか、時間をさかのぼる振り子の音を入れたりもしましたね。これは高校生の頃に書いたオリジナルにはもちろん入っていませんでした。ゲームに合わせて入れたものなんですけど。大元のメロディやコード進行は、高校生の頃に作ったものと同じです。
―― 光田さんが『クロノ・トリガー』の音楽を作曲されたのは、22歳くらいの頃ですよね。
光田 そうですね。『クロノ・トリガー』のプロジェクトが立ち上がってから、2年くらいずっとこまごまとやっていたんですけど、僕が22歳になるちょっと前に坂口さん(坂口博信氏)に音楽を作らせてほしいと直談判しに行って。その頃は『ライブ・ア・ライブ』がもう作られていて、『FF』も『V』が終わって『VI』に入るぐらいの時期でしたね。だから、曲を書き始めたのは22歳に入ってすぐか、21歳の終わりくらいから徐々にやりはじめたって感じだったと記憶しています。実質、制作をしていたのは22歳の時です。発売が、僕が23歳になってすぐだったので。しかも、サントラのライナーノーツを書いたのが、ちょうど僕の23歳の誕生日の時でしたから。
―― そうでしたね。やはり『クロノ・トリガー』は、光田さんにとって思い出深い作品でしょうか。
光田 思い出深いですね、良くも悪くも。というのは、良い部分では、やっぱりあの作品をやっていなかったら今の自分はないですね。悪い部分では、やっぱりあれがずっと引きずられているところはありますよね。音楽のクオリティ的には、今のほうが断然高いと思うんですけど。
『クロノ・トリガー』はやっぱり、みんなの思い出とか、当時の時代背景も含めて、とても強烈に印象に残っているところがあるので。“光田康典といえば『クロノ・トリガー』”という印象が、なかなか離れないっていうのはありますよね。まあそれは正直嬉しくもあり、くやしくもありますけど。でも、20年も前の作品を、今でも好きだと言っていただけるのは本当にありがたいことですね。だいたい今の世の中、曲が生まれても、どんどん埋もれていってしまうことが多いじゃないですか。悲しい現実ですよね。それを考えると、本当にありがたいことだと思います。
■「THE BRINK OF TIME」の裏話
―― 『クロノ・トリガー』のアレンジアルバム「THE BRINK OF TIME」は、ジャズ要素も取り入れられ、当時としては非常に先駆的なアレンジだったと感じました。ユーザーにとっても、すごく意外性があったと思うんですよ。
光田 むしろ、あれは批判が多かったですね。
―― 賛否両論というか、否のほうが多い感じでしたか?
光田 ええ。もし当時にTwitterとかFacebookがあったら、確実に炎上してるレベルですね!(笑)
―― (笑)。「THE BRINK OF TIME」は、どのようなテーマで作られたのでしょうか?
光田 当時のテーマとしては、“20年後に聴いても、かっこいいものを作ろう”というものだったんですよ。『クロノ・トリガー』のアレンジアルバムを作るにあたって、ただ単にオーケストラアレンジを作りました、みんなが求めているものを作りました、というのは面白くないなと思って。20年後、小学生や中学生だった子が、大人になって改めて聴いて、その良さがわかるような。久しぶりに『クロノ・トリガー』のアレンジでもちょっと聴いてみようかな、って聴いたら、「わっ、こんなことやってたんだ!」っていうのを作ろうというのがコンセプトだったんです。
当時、Jamiroquai(ジャミロクワイ)という、アシッドジャズ(※)のバンドがイギリスで流行っていたんですよ。当時はまだ日本では全然知られていないバンドだったんですけど、僕はJamiroquaiを知っていて。これからはアシッドジャズがちょっとブームになるかもしれないと思って、アシッドジャズで作ってみようと思ったんです。ほら、『ルパン三世』のテーマって、今聴いてもかっこいいじゃないですか。
※1980年代、ロンドンのクラブから流行したジャズの形態。
―― かっこいいですよね。
光田 ああいう感じですよ。
―― 光田さんは『ルパン三世』がお好きなんですよね。
光田 大好きです。だからそれもあるんですけど、ああやって何十年もずっと聴かれて、「わあ、今聴いてもかっこいいね」というのをやりたいな、という想いでああいうアレンジにしたんですけど……まあ、散々でしたよ。
―― でも、先日久しぶりに「THE BRINK OF TIME」を聴いたんですけど、1曲目の「CHRONO TRIGGER」からやられましたね。「かっこいい!」と思って。最初の足音のところとか、たまらないです。
光田 足音はね、当時杉並区にあった……今は新宿にありますけど、studio GREENBIRD(スタジオ グリーンバード)っていう、ほかのスタジオと全然比べものにならないくらいの、16型(※)の大きなオケでも余裕で入っちゃうほど広いスタジオがあったんですよ。
※オーケストラのサイズを表す呼称。第1ヴァイオリン奏者の人数により、16人=「16型」、14人=「14型」などとされている
で、そのすっごく広いスタジオにマイクを1本立てて、そこを歩いてもらって録音しました。あれは本物の足音なんですよ。
―― そうだったんですか。
光田 ラジカセを広いスタジオの真ん中に置いて、ラジカセまで歩いていって、ボタンをぽちっと押して去っていくっていう。あれはスタジオが広かったから出来た話なんですよ。今のスタジオじゃ絶対無理で。
―― 広いからこそ、反響音も入ったんですね。
光田 そう。ガレージっぽいサウンドですよね。ある意味、当時でしか録れない音でしたね。そう、その時にね、どの曲だったかな……、曲が綺麗にできあがったんですけど、ドラムの人に、「なんかおもしろくないから、ドラムスティック投げてください」って言って(笑)。バーッ、ドンガラガッシャン、みたいな音がちょっとだけ入ってます。ほとんど分からないですけど。でもそれがすごくいい味になっていたりしますね。あと、ギターアンプがいきなり燃え始めちゃったことがあったんですよ、スタジオの中で(笑)。
―― えええ!(笑)
光田 「それかっこいい!」って言って、そのまま弾いてもらって(笑)。実は、よく聴くと炎の音が入っていたりするんですよ。そんな逸話がたくさん残っているアルバムです。でもそういう事件がいまとなっては良い想い出ですね。
―― 作っていて、面白かったんですね。
光田 面白かったですよ。ムチャクチャですからね(笑)。今は絶対できないですよ、そんなこと。ムチャもいいところでしたよ。
■謎の楽曲「MITSUDA」
―― 『クロノ・トリガー』でずっと謎だったことがあったのでお聞きしたいのですが、DS版のサウンドテストの中に、「MITSUDA」という、光田さんの名前を冠した謎の曲があるんです。あれは一体何なのでしょうか?
光田 あれね、僕、まったく記憶にないんですよね。
―― 「てん、てててーてー、てんてん♪」という曲で、なぜか「MITSUDA」というタイトルで。あれが謎でしょうがなかったんですよ。
光田 いや、スーファミ版の時に、音色テストで色々ふざけたことはやっていたんですけど、それを入れた記憶は正直ないんですよね……。スーファミ版の製作当時は、制作途中の曲がROMに色々と入ってたんですけど、最終的には削らずにそのままROMに入っちゃったんですよね。
で、DS版ではインテリジェントシステムズさんの方がDSの音で内蔵音源化してくれたんですけど、スーファミ当時のまんまの音をなんとか再現しようとすごく頑張ってくれたんです。その時に、「この曲は本編に使われてるんですか?」みたいな曲がけっこう色々入ってたんですよ。「こんな曲書いたっけな?」みたいなものもあって。
―― まったく記憶に無い曲もあったんですね。
光田 ええ。なので、「それはいらないので、消しておいてください」って言ったんですけど、「いや、せっかくなので入れておきます」と言われて(笑)。うーん、「MITSUDA」か……なんだろう。DS版のサウンドテストで聴けるんですか?それは。
―― はい、DS版のサウンドテストに入ってました。
光田 …………あっ、思い出した! あれだ! 『クロノ・トリガー』のどれかのエンディングで、スタッフルームがあるじゃないですか。
―― はいはい、開発室ですね!
光田 そう! で、そこに僕も登場するんですけど、僕のところにメッセージが出終わったら、曲を流してくださいって注文しておいたんですよ。僕のメッセージは、やんわりと「僕は次の目標の為に旅にでます・・・要は会社をやめるかもしれない」っていうコメントなんですよね(笑)。そういうことを匂わせたコメントだったんです。
で、分かっちゃう人には分かっちゃうので「それは冗談だよ」という意味で、「MITSUDA」という曲を最後に流してほしかったんです。そうだ、思い出した。でも、それをやってくれなかったんですよね。「お前だけ音楽流すのはだめだ!」って(笑)。当時はまだ下っ端でしたから・・・。それを流してくれなかったので冗談ではなくなってしまったんですね・・・きっと(笑)
―― (笑) そうだったんですね。そういえば、光田さんは開発室でしゃべった後、どこかに去っていくんですよね。
光田 そうそう、そういう演出までやって。「僕は二度と帰ってこないようにしてください」って言いました。そういう演出のためにちょっとふざけて曲をいれたのが「MITSUDA」っていう曲ですね。他の曲に関してはちょっと覚えてないですけど。
―― あとDS版って、スーファミの時は未使用だった「歌う山」が使われているんですよね。
光田 そうなんですか? どのシーンで使われているかはまでは分からないんですけど、DS版の時は全曲を細かくチェックしましたよ。ほぼ原曲スーファミの音に近いところまで持っていきました。やっぱりスーファミの音源自体が古いものを使っていたので、どうしても再現できない音もあったんですけどね。今思うとどうやって作ったのか不思議ですね……。DS版が出た時は何歳くらいだったかな、35歳くらいかな。DS版っていつ出ましたっけ?
―― オリジナル版から13年後の発売なので、2008年ですね。
光田 2008年ということは35、6歳の時か。なんだか不思議な気持ちになりましたね、あれは。改めてスーファミの『クロノ・トリガー』の音を細かく聴くと、よく出来てるんですよね、やっぱり。13年も前に、色々と考えて自分は曲を作っていたんだなぁって、自分を改めて客観的に見た気がします。そうした意味でリメイクはいい仕事でしたね。
(おまけ話)植松氏との『moon』限定ユニット「あすなろボーイズ」
―― 1997年にプレイステーションで発売された作品『moon』では、植松伸夫さんと「あすなろボーイズ」というユニットを組まれて「くつしたの穴」という楽曲を書かれていましたが、どのような経緯で作られたのでしょうか?
光田 もう時効だから話してもいいかな(笑)。『moon』は、当時スクウェアにいた人たちが独立して、新しく作ることになったゲームだったんですよね。詳しい事はわからないのですが、たしか最初は植松さんに曲を書いてほしいというオファーが来たんですよ。内緒で1曲だけやってほしいと。その後、植松さんからコードとちょっとしたメロディが送られてきて、「光田さ、ちょっと一緒にやんない?」って言われて。「いいっすよ!」って引き受けて。で、僕、その時に猫のアコーディオンを作ってたんですよ。
―― 猫のアコーディオン……ですか!?
光田 そのへんにあります。植松さんに「僕ね、今アコーディオン作ってるんですよ」って言ったら「まじで!?」みたいな話になって。「じゃあ、それ曲に入れようよ!」って話になったんですよ。それそれ。ネコーディオンです!

―― おおー。かわいいですね!
光田 「くつしたの穴」の曲で使ったアコーディオンです。これ、下のシの音までしかないんですよ。植松さんのメロディには下のラが入ってたんですけど、「植松さん、鍵盤ないんですが!」って言ったら、「じゃあまかせる」って言われて。オクターブ上にしてなんとか演奏してレコーディングしました。
この曲は、誰がどの役割をやったかは植松さんと僕以外、たぶん誰も知らないでしょうね。僕がメロディのアコーディオンと、エレクトリックベースと、パーカッションを演奏して。植松さんはハーモニウムという鍵盤楽器を演奏しました。
―― このネコーディオンを「くつしたの穴」以外で使ったことはあるんですか?
光田 昔、僕のファンクラブのイベントのライブで使ったことはありましたね。この猫のデザインは自分でして、わざわざホームセンターに行って切り抜いたんですよ。
―― おお、ご自分で切られたんですね。
光田 はい、自分でやりました。だからすごく愛着があるんですよ。
光田 康典 プロフィール
Yasunori Mitsuda Profile
作曲家、編曲家、プロデューサー
1972年1月21日生まれ。1992年スクウェア(現スクウェア・エニックス)入社、1995年『クロノ・トリガー』で作曲家デビュー。『ゼノギアス』等の作曲を担当した後、1998年に独立。フリーランスで活動後、2001年プロキオン・スタジオを設立し、同社の代表を務める。以降、ゲームに限らず、テレビドラマ、アニメ、映画など多彩なジャンルの作曲活動を行う。またサラ・オレイン氏などアーティストのプロデュースや楽曲提供も手がけ、国内外のライブやコンサートにも積極的に出演している。
代表作:『クロノ・トリガー』『クロノ・クロス』『ゼノギアス』『ゼノサーガ エピソードI』『ソーマブリンガー』『イナズマイレブン』『新・光神話 パルテナの鏡』『ソウル・サクリファイス』『NHKスペシャル 宇宙生中継 彗星爆発 太陽系の謎』『黒執事 Book of Circus』他多数
■ミュージシャンの皆さんと共に作った「時の傷痕」
―― 光田さん、作曲家活動20周年おめでとうございます!
光田 ありがとうございます!
―― 今回は、光田さんのこれまでの活動を振り返りつつ、今後の活動の展望についてお聞きしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。
光田 こちらこそ、よろしくお願いします。
―― これまで光田さんは、本当に多くの作品の音楽を担当されてきましたが、今までに作曲された楽曲の中で、特に思い入れの深いものはありますか?
光田 本当にたくさん作ってきましたね。先日、僕が今までに作った楽曲を全部リスト化して数えてみたんですけど、CD化されていない楽曲も含めると、だいたい1,400曲くらいあったんですよ。
―― 1,400曲ですか!
光田 ええ。もうあんまり覚えていない作品もありましたけど(笑)、どの楽曲もそれぞれ思い出がありますね。その中から1曲挙げるとするなら、やっぱり『クロノ・クロス』の「CHRONO CROSS 〜時の傷痕〜」(以下「時の傷痕」)です。僕の場合は、コンピュータに楽曲を打ち込んでシミュレーションした後レコーディングすることが多いんですけど、「時の傷痕」は、レコーディングで劇的に素晴らしくなったんですよ。僕が打ち込みで作った原曲よりも、もう何倍も良くなったんですね。だからあの曲は、僕ひとりの力で作ったものではなくて、ミュージシャンの皆さんと一緒に、みんながひとつの想いで作ったから、世界に通用するような楽曲に仕上がったと思うんです。そういうことって、なかなか珍しいですね。
僕って、常に新しい人と何かをやりたいという思いがあるんです。でも、新しいことにチャレンジするということは、以前使った技みたいなものが使えないこともあるわけですよ。そうなると失敗しちゃうことも多々あるんですけど、「時の傷痕」のように、いろんな人の相乗効果で、自分が想像していた以上のものが出来あがったというのは本当に稀なケースなんです。最初、打ち込みで原曲を作った時は、「こんな曲で、大丈夫かな?」と思っていたんですけど、ミュージシャンの皆さんのおかげで素晴らしい楽曲になりました。
■前に突き進んでいくキッドに共感
―― 光田さんは、物語や、その中に登場するキャラクターに合わせて音楽を作るということが多かったと思うんです。光田さんの中で、特に思い入れの深いキャラクターはいらっしゃいますか?
光田 キャラクターですか。僕の中ではやっぱり、『クロノ・クロス』のキッドが非常に印象に残っていますね。
―― どのような点が印象的でしたか?
光田 彼女の生い立ちや設定に、共感できる部分がたくさんあったんですよ。僕も『クロノ・クロス』の制作当時はまだ20代だったんですけど、ひとつのものにがむしゃらに向かっていく感じがとても好きで。すごく共感できました。
―― なるほど……キッドといえば、やはり「星を盗んだ少女」という楽曲が印象深いです。キッドのテーマともいえる楽曲ですけど、光田さんの中でもやはり思い入れが深いのでしょうか?
光田 そうですね。あの楽曲って、最初はスーパーファミコンのサテラビューで配信された『ラジカル・ドリーマーズ -盗めない宝石-』というアドベンチャーゲームのために書いたんですけど、その当時からキッドという少女がすごく印象的だったんですよね。色々なものを背負っているけれど、前向きに、怒りをパワーにして前に突き進んでいくというキッドの姿勢にすごく心を打たれましたね。僕自身もそうありたいなという想いもあって、キッドはとても好きなキャラクターなんです。
■探し当てるように作った「SMALL TWO OF PIECES」
―― これまでに作られた楽曲の中で、いちばん苦しかった、難産だったものはありますか?
光田 『ゼノギアス』エンディングテーマの、「SMALL TWO OF PIECES 〜軋んだ破片〜」ですね。あれは本当に難産でした。僕が会社で曲を作っていた時も、「これでいいのか? これでいけるのか? どうなんだ?」みたいにずっと模索しつづけて。家に帰ってもひたすらコンピュータに向かって作ったり、何度もファイルをごみ箱に捨てたりの繰り返しでした。ひどいときは、ゴミ箱に捨てて小一時間ほど考えたあと、ごみ箱からまたファイルを戻して……というようなことをやっていたんです。
―― 相当、悩まれたんですね。
光田 はい。当時はオートバックアップも無かったので、捨てたらもう、それで終わりなんですよ。何度もごみ箱を空にするところまでやろうとしていたんですけど、でもなんとなく、原石というか、光るものがあると感じて……ちょっと気になっていたんですよ。「もうちょっと何とかすれば、いい曲になるんじゃないか」という感じだったんです。
―― 探し当てるような感じだったのでしょうか。
光田 探し当てる……。そうですね。本当に、作曲って作業はそういう感じです。パーッと作って、はい、できました!というものじゃなくて、僕の場合は「このコードで本当に正解なのか?」「このメロディで本当にいいのか?」っていうのを、何度も何度も聴きながら、繰り返し練っていくんですよね。だから時間はかかりますけど、やっぱり僕は皆さんの印象に残る楽曲を作りたいと思っていますからね。あれは本当に難産でした。でも、ジョアンヌ・ホッグの歌が曲に入った瞬間に、本当に救われた気持ちになりましたよ。「これ、捨てなくてよかったなぁ」って。報われました。……もし、あれを捨てていたらどんな曲になっていたんでしょうね(笑)。それはちょっと聴いてみたいかな。
■“テーマ”を決めてつくる
―― 光田さんはこれまで多数の作品を手がけられてきましたが、ご自身が作曲家として最も成長できたと感じる作品はありますか?
光田 僕が今までに手掛けた作品すべてですね。何かの作品を作るたびに勉強になります。僕の音楽の作り方としては、作品ごとに“テーマ”を決めてやるんですよ、常に。
―― “テーマ”ですか。
光田 ええ。何か自分の苦手なこと……たとえば、オーケストレーションが苦手だったらそれを克服しようとか。何かの楽器が不得意なら、その楽器をとことん研究してやってみようとか。そういうことですね。
僕、『クロノ・クロス』の頃はギターが苦手だったんですよ。サウンドとしては好きなんだけど、演奏するとなると、どんなふうに弦を押さえたらいいか分からない(笑)。なので、その頃からギターを買って勉強して。『クロノ・クロス』はギターサウンドで行こう、というテーマがありました。
『クロノ・トリガー』はいろんな時代に行くので、いかに楽曲のモチーフを組み合わせて印象的なゲームにしていくか、ということがテーマでしたし。『ゼノギアス』は、生録音の音楽や、歌ものを入れるというテーマでした。それぞれの作品にテーマを設けて作ってきましたね。
―― 『ゼノサーガ エピソードI』では、オーケストラでの音楽を作られていましたね。
光田 そうですね。初めてオーケストレーションをしました。それまでにも勉強はしていたんですけど、やっぱり書物で勉強しているだけのものと、本物のオーケストラで実際に演奏してもらうのとでは、大きな差があるんですよね。音楽理論的に説明されていることでも、その通りにやっても意外に綺麗に鳴らなかったりするんです。それは何故かと言うと、ミュージシャンの気持ちもあるし、技量もあるし。スタジオの状態やエンジニアの技量など、本当にいろんな要素があるんです。
そして、理論というのは「大体うまくいくであろう」ということが本になっているわけですから、それをその通りにやったからって、必ずしもうまくいくわけではないんですよ。やっぱり色々と四苦八苦して、オーケストラと共に、自分の納得がいくサウンドを作り上げていくわけです。とにかく経験あるのみなんですよね。何度も失敗しては自分の理想に近づいていくわけです。間違いなく『ゼノサーガ エピソードI』の時よりも、今のほうがオーケストレーションの技量は上達していると実感しています。作品ごとに学ぶことは多いですよ。そういった意味では、やはりテーマを設けて作っていくのは、僕にとってすごく重要なことですね。
―― 作品ごとに新しいことに挑戦して、勉強して、よりよいものを作るということですね。
光田 はい、勉強して。……まあ、大変ですけどね(笑)。
―― 光田さんはいい音を録るためなら、自腹で費用を出してでもレコーディングを続行することがあるとお聞きしたのですが。
光田 そうですね。やっぱり自分が胸を張って、「この作品はお気に入りなんです」って言える状態にしないと。多少お金がかかっても、もう1回レコーディングしていい音が録れるんだったら、やればいい話じゃないですか。それを、数万円とか数十万円をケチって作品の質が下がるのは、ユーザーの皆さんに対しても失礼ですからね。ユーザーの皆さんは、お金を出して作品を買ってくれるわけですし、やっぱり、それ相応の作品を提示するというのがクリエイターの義務だと思います。僕自身が胸を張って出せるような作品を、これからも常に作っていきたいですね。
■『シャドウハーツ』の弘田佳孝氏と共作して気づいたこと
―― この20年の中で、転機になった作品はありますか?
光田 転機になったのは、『ゼノサーガ エピソードI』を終えた時ですね。あの作品の音楽を作り終えた時、僕の中で完全にからっぽになっちゃったんですよ。今思えば、特に完璧ではなかったのにも関わらず、自分はやり尽くしたような気になっちゃって……。もうロンドンフィルでレコーディングしたし、もうやること無くなっちゃったなって、勝手に思っちゃったんですよね、その時。
で、当時はずっと曲が書けないまま、『シャドウハーツ』という作品を担当することになって。この作品では、弘田佳孝君という作曲家と一緒に音楽を作ったんです。彼は現在、EARTHBOUND PAPAS(植松伸夫氏がリーダーを務めるバンド)のベースをやってますね。じつは彼と僕は、音楽学校が同じで、同級生だったんですよ。
―― そうだったんですか。
光田 ええ。スクウェアで効果音の制作者が必要になった時に、彼を招集して効果音を作ってもらうことになって、そこからゲーム音楽の世界に入ってきたんですけど。彼はもともとすごいロックとか、そっちの方向の人間なんですよ。で、彼と一緒に『シャドウハーツ』の音楽を作ることになったんですけど、僕は当時完全に抜けがら状態になっていたので、正直に言って、あんまり気が進まなかったんですよね。でも、一緒にやって気づいたことがあるんです。彼の音楽スタイルって、非常にアバンギャルドで発想が大胆なんですよ。音の鳴りが良いとか悪いとかじゃなくて、“今、この音が欲しいんだ!”みたいな、そういうパワーをすごく感じて。「そうだな……音楽って、そもそも綺麗に作ろうとかじゃなくて、自分が欲しい音を鳴らせばいいんだ」ということに気づかされたんです。
―― 弘田さんと共作することで、そう感じられたのですね。
光田 そうですね。音を置くのが怖い時期でもありましたので、彼とやることによってもっと自由に音楽を作ればいいんだ、と気づきました。自分がずっと悩んでいたことが、少し緩和された感じでしたね。
―― ある意味、吹っ切れたような。
光田 うん、吹っ切れた部分はありますね。結果的に『シャドウハーツ』の音楽は、僕の中でも非常に特殊なサウンドになったと思うんですよね。なので、あれは僕のひとつの転機になりましたね。『ゼノサーガ エピソードI』から『シャドウハーツ』の間は、僕の中ではすごく葛藤があったんですけど、非常に重要な時期だったと思います。
■演劇から学んだこと
―― では次に、だいぶ昔のことになるのですが、光田さんの若いころのお話をお聞きしていきたいと思います。光田さんは学生時代に演劇の音効さん(音響効果)をされていたそうですね。
光田 はい、やっていました。
―― その時のご経験で糧になったことはありますか?
光田 当時、とある劇団の専属音効をしていまして、完全に任されていました。まあ、しがない小さな劇団だったので、ノーギャラでやるようなレベルですけどね。お客さんも本当にまばらで50人入ればいいほう、みたいな劇団だったんですけど。選曲から音の当て方まで、全部好きなようにやっていいよっていうことで、僕が知っている曲を当てたり、足りない曲は自分で書いたりして音楽を流していたんですよ。
その経験から勉強になったのは、「セリフと音楽の関係」ですね。間があって、ここのタイミングで音楽が流れ始めるとか。静寂の中の一拍、みたいな。ああいう本当にちょっとした間で、人間の感情って大きく左右されるんだな、ということをその演劇で学ばせてもらいましたね。それがたぶん『クロノ・トリガー』にも息づいていると思いますし。音楽と映像、音楽と俳優の演技、音楽とセリフ……そういったことを考えて、ベストなタイミングにベストな音楽を鳴らす、という。そういうことを学ばせていただいた場所でしたね。
■桜庭統さんのアシスタント時代のお話
―― 光田さんは、桜庭統さんのアシスタントをされていたことがあるとお聞きしまして。
光田 はい。
―― 桜庭さんがウルフチーム(※)に在籍されていた頃ですよね。
※かつて存在したゲーム制作会社。日本テレネット内の開発チーム「ウルフチーム」が独立し、1987年に設立された。
光田 そうです。僕がまだ18歳の頃ですね。当時僕は東京に来てアルバイトを探していたんですけど、どうせアルバイトをするなら何か音楽関係の仕事をやりたいなと。やっぱり音楽漬けになりたいという思いがあって、色々探してたんですよ、フロムエーとかで(笑)。そしたらゲーム開発で、シンセサイザーマニピュレーターの募集があって。そこがウルフチームだったんです。会社の場所も、当時僕が通っていた学校から近くていいなと思って応募したら、受かっちゃったんです。
で、いざ中に入ってみたら、僕の隣の席で、桜庭さんがキーボードでガンガン曲を書いてるんですよ。僕はFM音源で楽器の音色を作るんですけど、もう、桜庭さんからどんどんどんどん曲があがってくるんですよ。本当に1時間に1曲くらいのペースで作ってて。
―― 桜庭さん、当時から作曲速度が早かったんですね(笑)。
光田 うん、メッチャ早いんですよ。桜庭さんが「これ、できたから音色よろしく」って曲を渡してくるんですけど、もう僕が音色を作るほうが間に合わないんですよ(笑)。早すぎるでしょ!って。
―― (笑)。すごいですね…!
光田 すごかったです、本当に。もう、弾いたらOKみたいな感じですよ。キーボードを弾いて、どんどんベースやドラム入れて、はい、終わりみたいな。それでクオリティが低いかっていうと、全然そんなことはなくて、ちゃんとした音楽になってるんですよね。桜庭さんの手クセは入ってるんですけど、クオリティ的には、当時のゲームの音楽としては非常に高かったんです。
そうやって桜庭さんから曲をもらって、僕は「じゃあ、このサウンドならこういう音がいいですよね」とか言いながら、FM音源で音色を作っていました。当時はパソコンゲームですから、PC-98とかPC-88の時代ですね。
―― FM音源が主流の頃ですね。
光田 そうですね。それにプラスして、PCM音源もちょっと入っていたぐらいだと思うんですけど。そのマニピュレーターをやっていました。
―― 光田さんが、桜庭さんから学んだことはありましたか。
光田 それが、あまりお話する機会がなかったんですよ。桜庭さんはずっと無口で、ひたすら曲を書く方でしたから。で、定時になったら「おつかれ」と言って帰っていって。あと、僕の作った音色に対しても、「この音色はイヤだ」とか、そういうことは一切言わなかったんですよ。
―― リテイクは少なかったのでしょうか?
光田 リテイクは、ほんとに数回だけでしたね。「ちょっとベースの音が柔らかいね」とか。「わかりました」って直したりしてね。
―― では、お話しされるのも本当にそういう時だけだったんですね。
光田 うん、そのくらいしかしゃべらなかったんですよ。でも、当時のことを桜庭さんは今も覚えてくれていて、お会いすると「いやー、あの光田君がねぇ」と言ってくれます。まあ僕は、1年ぐらいでウルフチームを辞めちゃったんですけどね。当時は機材の進化が目まぐるしかったんですよ。FM音源もあれば、加算式シンセだとか、アナログシンセ、サンプラーも色々ありましたし。あとPCM音源もどんどん進化していきましたから、その中でずっとFM音源で音色を作る意味合いを見い出せなくなっちゃった部分があって。
でも、曲を書かせてもらいたいと思ったことはないんですよ、当時は。ウルフチームで働いていたのは、音色作りとか、ゲームってどんな風に作られているんだろう?というのを学びたかったからなんです。とっても勉強になりましたね。
そういえば、当時スゴかったですよ、ウルフチームって。今では当たり前ですけど、カードをピッてやると、ドアがヒューッと開いて。「おーすげぇー、SFだーここ!」みたいな(笑)。「なんだここ! 『2001年宇宙の旅』にやってきたのか!(笑)」みたいな未来感に圧倒されましたね。すごくいい思い出です。
■効果音制作の醍醐味
―― 光田さんは『クロノ・トリガー』で作曲を担当される前に、効果音を担当されていましたよね。
光田 はい。いわゆるマニピュレーターもそうですね。
―― 光田さんが効果音を担当された作品は、『ファイナルファンタジーV』、『聖剣伝説2』、『ロマンシング サ・ガ2』などですよね。音楽を作るのとは、また違う面白さがありましたか?
光田 そうですね、非常に楽しくやらせてもらいました。『聖剣伝説2』はほとんど、ほぼ80%くらいは僕の作った音で出来ています。
―― 『聖剣伝説2』はクオリティの高い音楽でしたけど、効果音が鳴ると、その音で音楽が部分的に消えてしまうこともありましたよね。そのあたりの工夫は何かされていましたか?
光田 スーパーファミコンって、8トラックしかなかったんですよね。1トラック1音しか鳴らせないんですよ。菊田さん(『聖剣伝説2』の作曲家・菊田裕樹氏)が書いた曲はパーカッションが多かったので、多少は助かったんですけどね。まあたぶん、それは効果音で音楽が消されるだろうから、パーカッションを多めに入れよう、という風に菊田さんが考慮してくれたんだと思うんですけど。
で、効果音も、当時は2トラックを使って、ちょっとしたノイズ音でも、音をずらしてワイド感を出したり、モジュレーションを上手く使ったりとか、色々な技があったんですよね。でも当時2トラックで1つの効果音、たとえば「ザッ」という剣で斬る音を、2回連続で「ザザッ」というふうに鳴らしてしまうと、もうそれで4トラック使っちゃうことになるんですよ。そうすると残り4トラックしか無いから、ほとんど音楽が削られてよく分からない状態になってしまうんです。
だから、1音でちゃんと剣の音が成り立つようにしようと思いました。例えば、剣や足音のように頻繁に鳴る効果音ですよね。そういうものは1音で効果音を作っていました。大事なシーンは、すごくゴージャスに効果音を作ったりもしましたけどね。例えば『FFV』の飛竜の鳴き声とか。あれは非常に面白かったです。
―― 飛竜の鳴き声は光田さんが作られたんですね。
光田 はい、僕が作りました。
―― たしか、シルドラの鳴き声も光田さんが作られたんですよね?
光田 シルドラもそうです。動物の鳴き声系は全部僕ですね。
―― 当時『FFV』をプレイしていて、飛竜の鳴き声はとても印象的でしたよ。シルドラが渦に飲みこまれていってしまうシーンとか、すごく悲しげな声で。
光田 もう悲鳴みたいな感じですもんね。ぜんぜん実際の悲鳴には遠く及ばないんですけど。あと『ロマサガ2』も、ほとんど僕が効果音を作りましたね。ピコーンっていう音とか。
―― 電球の音ですね(笑)。
光田 はい。技をひらめいた時の電球の音ですね。イトケンさん(伊藤賢治氏)に、ラジオかなんかに一緒に出演しているときに「これもう1回作ってよ!」って言われたことがあるんですけど、「いや、今さら作れないでしょ!」って(笑)。
■SFC版『半熟英雄』の裏話
光田 あとは、スーパーファミコン版の『半熟英雄』で、すぎやまこういち先生が作曲した音楽のサウンドデザイン(ゲーム音源の制作)も担当させていただきました。
―― 『半熟英雄』も担当されていたのですか。
光田 はい、『半熟英雄』の音色を作らせてもらいました。すぎやま先生からスクウェアに、FAXで手書きの譜面が送られてくるんですよ。当時はまだ譜面なんです。MIDIデータの交換という概念があまり無い頃だったので、譜面がパーッとFAXで送られてきて。
その譜面をもとに僕がMIDIで打ち込んでいって、すぎやま先生のご自宅にお伺いして「こんな感じでどうでしょう?」とお聴かせしてチェックしていただいて。けっこう細かくアドバイスしていただきました。「マリンバがちょっと柔らかすぎる」とか、「エレピとフルートはこのバランスで」みたいな。あと、アーティキュレーション(※)のことをすごく言われました。「アタック(※)の位置はいいんだけど、リリース(※)が悪いね」とか。
※アーティキュレーション…… ある音から次の音へ、どのように移ってゆくかを表す音楽用語。音をなるべくつなげて演奏する「レガート」、音を短く切って演奏する「スタッカート」などがある。
※アタック…… 音の出だしのこと。
※リリース…… 音の鳴り終わりのこと。
―― すぎやま先生のアドバイスをもとに、MIDIデータを修正したわけですね。
光田 ええ。でも、FAXで譜面が送られてくると、譜面が潰れていて見えないことがあるんですよ。どっちとも取れる、みたいな。こっちでも間違いじゃないんだけど、こっちでも間違いじゃないとか。
そういう音を、「たぶん、これはこっちだろうな」って作って持って行くと、「光田くん、音間違えてるよ」って言われて(笑)。「だって譜面が見づらいんですもん!」とか心の中で思ってました(笑)。
―― (笑)。FAXですもんね。
光田 そうなんですよ。そんなやりとりがありました。でもすぎやま先生、とてもパワフルな方でしたね。その当時でもかなりのお歳だったと思うんですけど、バリバリに作曲されていましたよ。
■加藤正人氏と大ゲンカ!
―― 光田さんは若い頃かなり熱い方だったそうですが、光田さんご自身が昔を振り返って、「自分は熱かったなぁ」と感じる思い出はありますか?
光田 『クロノ・トリガー』を作っていた当時、加藤さん(加藤正人氏。『ゼノギアス』、『クロノ・クロス』など多数の作品で演出やシナリオを担当)のシナリオをプリントアウトして自分のブースで読んでいたんですよ。「曲をここに入れよう」とか考えながら。
そうしたら、どうしてもつじつまが合わない、「なんでこの設定なんだろう?」と思うことがあって。加藤さんのブースに乗り込んで、「これどういう設定してんの?こんなの全然ダメじゃん!」って話をしたんです。それですごい言い争いになったんです、加藤さんと。「これはこうで、こうだよ!」とか。挙げ句の果てに、「もうやってらんない!」って叫んで、紙っぺらを加藤さんに投げつけて、自分のブースに帰っていった覚えがあります。
―― えええ……!
光田 まわりの制作メンバーのみんなは、びっくりして一斉に立ちあがってましたよ(笑)。「光田と加藤がすっげえ大ケンカしてる……」って唖然としちゃって。そんなことがありました。加藤さんはその出来事を全然覚えてないんですけど、僕はすごく覚えてます。その設定に対してすっごく激怒した覚えがあります。若かったですね(笑)。今は絶対そんなことはないですけど。
―― 光田さんは、なぜそんなに怒ったのでしょうか?
光田 あれはね、サラの立ち位置でケンカになったんですよね。なんか最初、とんでもない設定だったんですよ、それが気に入らないって言って。
―― けっこう突拍子もない設定だったのですか?
光田 そうなんですよ。まったく意味がわからなくて。それでケンカした覚えがあります。加藤さんはたぶん「そんなことあったっけ?」って言うでしょうけど(笑)。
■若い人は、熱く突き進んでほしい
―― 光田さんは色々なご経験をされてきたと思うのですが、若い世代の方にアドバイスするとしたら何かありますか。
光田 アドバイスですか……まあ、僕は若い頃は熱かったので、今の若い人も、熱い感じなのがいいんじゃないですかね。何事も熱く(笑)。
―― 若いパワーで。
光田 そうそう。若い時しかできないことってたくさんあるじゃないですか。だから僕、若い人がなりふり構わず「これはどうなんだ!」みたいなことを言うのがすごく好きなんですよね。「これをやりたいんだ、なんでやらせてくれないの!」とか、そういう熱い人をみると、こっちも、「じゃあ、それをやってみれば」ってなりますし。特に、外国の人なんかどんどん自分をアピールして来るじゃないですか。「これをやりたいんだ!」とかね。そういう熱い気持ちを持ってる人って気持がいいですよね。結局それって、すごく自分に自信をもっていて、その事にたいして好きじゃないと出来ないと思うんですよ。
―― そうですよね。
光田 その物事に対してすごく熱くなれる、「誰よりも自分は熱くなれる」っていう、そういう想いが無いとなかなか良いものも出来ないですしね。逆に言えば、そういう気持ちが無いんだったら、物作りは辞めたほうがいいでしょうね。熱い気持ちをもって突き進めば、必ず成功すると思っています。
たぶん、誰しも自分がなりたいものや、やりたいことなどは実現すると思うんですよ。でも結局、その途中で熱が冷めちゃったり、現実に戻っちゃったりして諦めてしまうんですよね。もちろん、経済的な問題もあるだろうし、気持ち的な問題もあるだろうし、対人関係という問題もあるでしょう。でもそこを差し置いても、自分が何をしたいのか、何を表現したいのかということが、ぶれずに突き進める熱い人は、成功すると思いますし、たくさんライバルがいる中でも生き残っていけるんじゃないかなと思います。
■「遥かなる時の彼方へ」に込められた想い
―― 次は『クロノ・トリガー』に関するお話をお聞きしていければと思います。エンディングテーマ「遥かなる時の彼方へ」は、『クロノ・トリガー』のゲーム制作前に作られた、とある人のために書いた楽曲だとお聞きしました。どのような想いが込められている楽曲なのか、お聞かせいただければと思います。
光田 そうですね……実は、僕が高校生くらいの時には、すでにあの曲を作っていたんです。僕が高校2年生くらいの時だったかな。カモンミュージックというシーケンサーをバイトして買って、自分で色々と曲を好きに作っていたんですよ。
その当時に、大の親友が亡くなってしまって、その人のために書いた曲だったんですね。あの曲は本当に、思い入れがあるというか、別格です。何かのテーマがあって、ゲームに宛てた曲ではないので。ちょっとニュアンスが違うんですよね。
―― その曲を、なぜ『クロノ・トリガー』で使用することになったのでしょうか?
光田 『クロノ・トリガー』のエンディングと、なんかリンクしちゃったんですよね、僕の中で。別れは切ないけどちょっと前向きな、そういうイメージが。まあ、本当は使わないようにしようと思ったんですけど、『クロノ・トリガー』の最後のお話を読んでいた時に、なんとなくずっと気になってて。自分の経験とゲームの話と音楽がリンクしちゃって。
―― やっぱり使おう、と思われたわけですか。
光田 なんとなくですね。これはやっぱり使うべきだろうなと。あと、「遥かなる時の彼方へ」には、最後に『クロノ・トリガー』のテーマが入っていたりとか、時間をさかのぼる振り子の音を入れたりもしましたね。これは高校生の頃に書いたオリジナルにはもちろん入っていませんでした。ゲームに合わせて入れたものなんですけど。大元のメロディやコード進行は、高校生の頃に作ったものと同じです。
―― 光田さんが『クロノ・トリガー』の音楽を作曲されたのは、22歳くらいの頃ですよね。
光田 そうですね。『クロノ・トリガー』のプロジェクトが立ち上がってから、2年くらいずっとこまごまとやっていたんですけど、僕が22歳になるちょっと前に坂口さん(坂口博信氏)に音楽を作らせてほしいと直談判しに行って。その頃は『ライブ・ア・ライブ』がもう作られていて、『FF』も『V』が終わって『VI』に入るぐらいの時期でしたね。だから、曲を書き始めたのは22歳に入ってすぐか、21歳の終わりくらいから徐々にやりはじめたって感じだったと記憶しています。実質、制作をしていたのは22歳の時です。発売が、僕が23歳になってすぐだったので。しかも、サントラのライナーノーツを書いたのが、ちょうど僕の23歳の誕生日の時でしたから。
―― そうでしたね。やはり『クロノ・トリガー』は、光田さんにとって思い出深い作品でしょうか。
光田 思い出深いですね、良くも悪くも。というのは、良い部分では、やっぱりあの作品をやっていなかったら今の自分はないですね。悪い部分では、やっぱりあれがずっと引きずられているところはありますよね。音楽のクオリティ的には、今のほうが断然高いと思うんですけど。
『クロノ・トリガー』はやっぱり、みんなの思い出とか、当時の時代背景も含めて、とても強烈に印象に残っているところがあるので。“光田康典といえば『クロノ・トリガー』”という印象が、なかなか離れないっていうのはありますよね。まあそれは正直嬉しくもあり、くやしくもありますけど。でも、20年も前の作品を、今でも好きだと言っていただけるのは本当にありがたいことですね。だいたい今の世の中、曲が生まれても、どんどん埋もれていってしまうことが多いじゃないですか。悲しい現実ですよね。それを考えると、本当にありがたいことだと思います。
■「THE BRINK OF TIME」の裏話
―― 『クロノ・トリガー』のアレンジアルバム「THE BRINK OF TIME」は、ジャズ要素も取り入れられ、当時としては非常に先駆的なアレンジだったと感じました。ユーザーにとっても、すごく意外性があったと思うんですよ。
光田 むしろ、あれは批判が多かったですね。
―― 賛否両論というか、否のほうが多い感じでしたか?
光田 ええ。もし当時にTwitterとかFacebookがあったら、確実に炎上してるレベルですね!(笑)
―― (笑)。「THE BRINK OF TIME」は、どのようなテーマで作られたのでしょうか?
光田 当時のテーマとしては、“20年後に聴いても、かっこいいものを作ろう”というものだったんですよ。『クロノ・トリガー』のアレンジアルバムを作るにあたって、ただ単にオーケストラアレンジを作りました、みんなが求めているものを作りました、というのは面白くないなと思って。20年後、小学生や中学生だった子が、大人になって改めて聴いて、その良さがわかるような。久しぶりに『クロノ・トリガー』のアレンジでもちょっと聴いてみようかな、って聴いたら、「わっ、こんなことやってたんだ!」っていうのを作ろうというのがコンセプトだったんです。
当時、Jamiroquai(ジャミロクワイ)という、アシッドジャズ(※)のバンドがイギリスで流行っていたんですよ。当時はまだ日本では全然知られていないバンドだったんですけど、僕はJamiroquaiを知っていて。これからはアシッドジャズがちょっとブームになるかもしれないと思って、アシッドジャズで作ってみようと思ったんです。ほら、『ルパン三世』のテーマって、今聴いてもかっこいいじゃないですか。
※1980年代、ロンドンのクラブから流行したジャズの形態。
―― かっこいいですよね。
光田 ああいう感じですよ。
―― 光田さんは『ルパン三世』がお好きなんですよね。
光田 大好きです。だからそれもあるんですけど、ああやって何十年もずっと聴かれて、「わあ、今聴いてもかっこいいね」というのをやりたいな、という想いでああいうアレンジにしたんですけど……まあ、散々でしたよ。
―― でも、先日久しぶりに「THE BRINK OF TIME」を聴いたんですけど、1曲目の「CHRONO TRIGGER」からやられましたね。「かっこいい!」と思って。最初の足音のところとか、たまらないです。
光田 足音はね、当時杉並区にあった……今は新宿にありますけど、studio GREENBIRD(スタジオ グリーンバード)っていう、ほかのスタジオと全然比べものにならないくらいの、16型(※)の大きなオケでも余裕で入っちゃうほど広いスタジオがあったんですよ。
※オーケストラのサイズを表す呼称。第1ヴァイオリン奏者の人数により、16人=「16型」、14人=「14型」などとされている
で、そのすっごく広いスタジオにマイクを1本立てて、そこを歩いてもらって録音しました。あれは本物の足音なんですよ。
―― そうだったんですか。
光田 ラジカセを広いスタジオの真ん中に置いて、ラジカセまで歩いていって、ボタンをぽちっと押して去っていくっていう。あれはスタジオが広かったから出来た話なんですよ。今のスタジオじゃ絶対無理で。
―― 広いからこそ、反響音も入ったんですね。
光田 そう。ガレージっぽいサウンドですよね。ある意味、当時でしか録れない音でしたね。そう、その時にね、どの曲だったかな……、曲が綺麗にできあがったんですけど、ドラムの人に、「なんかおもしろくないから、ドラムスティック投げてください」って言って(笑)。バーッ、ドンガラガッシャン、みたいな音がちょっとだけ入ってます。ほとんど分からないですけど。でもそれがすごくいい味になっていたりしますね。あと、ギターアンプがいきなり燃え始めちゃったことがあったんですよ、スタジオの中で(笑)。
―― えええ!(笑)
光田 「それかっこいい!」って言って、そのまま弾いてもらって(笑)。実は、よく聴くと炎の音が入っていたりするんですよ。そんな逸話がたくさん残っているアルバムです。でもそういう事件がいまとなっては良い想い出ですね。
―― 作っていて、面白かったんですね。
光田 面白かったですよ。ムチャクチャですからね(笑)。今は絶対できないですよ、そんなこと。ムチャもいいところでしたよ。
■謎の楽曲「MITSUDA」
―― 『クロノ・トリガー』でずっと謎だったことがあったのでお聞きしたいのですが、DS版のサウンドテストの中に、「MITSUDA」という、光田さんの名前を冠した謎の曲があるんです。あれは一体何なのでしょうか?
光田 あれね、僕、まったく記憶にないんですよね。
―― 「てん、てててーてー、てんてん♪」という曲で、なぜか「MITSUDA」というタイトルで。あれが謎でしょうがなかったんですよ。
光田 いや、スーファミ版の時に、音色テストで色々ふざけたことはやっていたんですけど、それを入れた記憶は正直ないんですよね……。スーファミ版の製作当時は、制作途中の曲がROMに色々と入ってたんですけど、最終的には削らずにそのままROMに入っちゃったんですよね。
で、DS版ではインテリジェントシステムズさんの方がDSの音で内蔵音源化してくれたんですけど、スーファミ当時のまんまの音をなんとか再現しようとすごく頑張ってくれたんです。その時に、「この曲は本編に使われてるんですか?」みたいな曲がけっこう色々入ってたんですよ。「こんな曲書いたっけな?」みたいなものもあって。
―― まったく記憶に無い曲もあったんですね。
光田 ええ。なので、「それはいらないので、消しておいてください」って言ったんですけど、「いや、せっかくなので入れておきます」と言われて(笑)。うーん、「MITSUDA」か……なんだろう。DS版のサウンドテストで聴けるんですか?それは。
―― はい、DS版のサウンドテストに入ってました。
光田 …………あっ、思い出した! あれだ! 『クロノ・トリガー』のどれかのエンディングで、スタッフルームがあるじゃないですか。
―― はいはい、開発室ですね!
光田 そう! で、そこに僕も登場するんですけど、僕のところにメッセージが出終わったら、曲を流してくださいって注文しておいたんですよ。僕のメッセージは、やんわりと「僕は次の目標の為に旅にでます・・・要は会社をやめるかもしれない」っていうコメントなんですよね(笑)。そういうことを匂わせたコメントだったんです。
で、分かっちゃう人には分かっちゃうので「それは冗談だよ」という意味で、「MITSUDA」という曲を最後に流してほしかったんです。そうだ、思い出した。でも、それをやってくれなかったんですよね。「お前だけ音楽流すのはだめだ!」って(笑)。当時はまだ下っ端でしたから・・・。それを流してくれなかったので冗談ではなくなってしまったんですね・・・きっと(笑)
―― (笑) そうだったんですね。そういえば、光田さんは開発室でしゃべった後、どこかに去っていくんですよね。
光田 そうそう、そういう演出までやって。「僕は二度と帰ってこないようにしてください」って言いました。そういう演出のためにちょっとふざけて曲をいれたのが「MITSUDA」っていう曲ですね。他の曲に関してはちょっと覚えてないですけど。
―― あとDS版って、スーファミの時は未使用だった「歌う山」が使われているんですよね。
光田 そうなんですか? どのシーンで使われているかはまでは分からないんですけど、DS版の時は全曲を細かくチェックしましたよ。ほぼ原曲スーファミの音に近いところまで持っていきました。やっぱりスーファミの音源自体が古いものを使っていたので、どうしても再現できない音もあったんですけどね。今思うとどうやって作ったのか不思議ですね……。DS版が出た時は何歳くらいだったかな、35歳くらいかな。DS版っていつ出ましたっけ?
―― オリジナル版から13年後の発売なので、2008年ですね。
光田 2008年ということは35、6歳の時か。なんだか不思議な気持ちになりましたね、あれは。改めてスーファミの『クロノ・トリガー』の音を細かく聴くと、よく出来てるんですよね、やっぱり。13年も前に、色々と考えて自分は曲を作っていたんだなぁって、自分を改めて客観的に見た気がします。そうした意味でリメイクはいい仕事でしたね。
(おまけ話)植松氏との『moon』限定ユニット「あすなろボーイズ」
―― 1997年にプレイステーションで発売された作品『moon』では、植松伸夫さんと「あすなろボーイズ」というユニットを組まれて「くつしたの穴」という楽曲を書かれていましたが、どのような経緯で作られたのでしょうか?
光田 もう時効だから話してもいいかな(笑)。『moon』は、当時スクウェアにいた人たちが独立して、新しく作ることになったゲームだったんですよね。詳しい事はわからないのですが、たしか最初は植松さんに曲を書いてほしいというオファーが来たんですよ。内緒で1曲だけやってほしいと。その後、植松さんからコードとちょっとしたメロディが送られてきて、「光田さ、ちょっと一緒にやんない?」って言われて。「いいっすよ!」って引き受けて。で、僕、その時に猫のアコーディオンを作ってたんですよ。
―― 猫のアコーディオン……ですか!?
光田 そのへんにあります。植松さんに「僕ね、今アコーディオン作ってるんですよ」って言ったら「まじで!?」みたいな話になって。「じゃあ、それ曲に入れようよ!」って話になったんですよ。それそれ。ネコーディオンです!

―― おおー。かわいいですね!
光田 「くつしたの穴」の曲で使ったアコーディオンです。これ、下のシの音までしかないんですよ。植松さんのメロディには下のラが入ってたんですけど、「植松さん、鍵盤ないんですが!」って言ったら、「じゃあまかせる」って言われて。オクターブ上にしてなんとか演奏してレコーディングしました。
この曲は、誰がどの役割をやったかは植松さんと僕以外、たぶん誰も知らないでしょうね。僕がメロディのアコーディオンと、エレクトリックベースと、パーカッションを演奏して。植松さんはハーモニウムという鍵盤楽器を演奏しました。
―― このネコーディオンを「くつしたの穴」以外で使ったことはあるんですか?
光田 昔、僕のファンクラブのイベントのライブで使ったことはありましたね。この猫のデザインは自分でして、わざわざホームセンターに行って切り抜いたんですよ。
―― おお、ご自分で切られたんですね。
光田 はい、自分でやりました。だからすごく愛着があるんですよ。
⇒【後編】光田康典 作家20周年記念インタビュー ― 遥かなる時の彼方へ ―
Copyright (c) 2083 All Right Reserved.